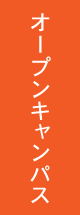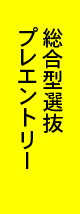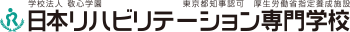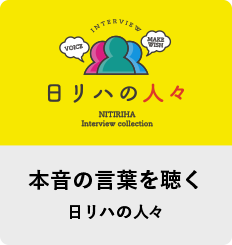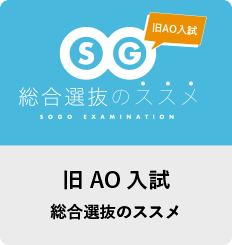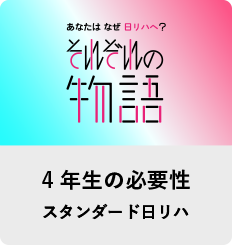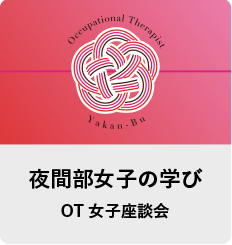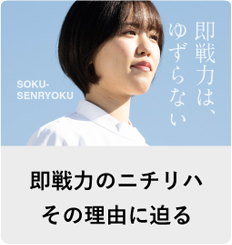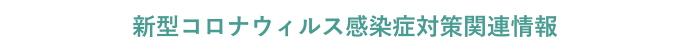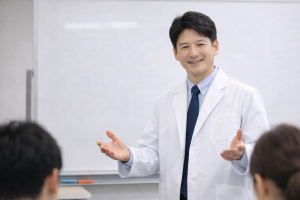
理学療法士国家試験の合格率や難易度、受験資格・内容を解説
監修:日本リハビリテーション専門学校 鍋城武志(理学療法士)
理学療法士になるために必須となる国家試験の全体像を解説します。
本記事では、試験の難易度を示す合格率の推移から、具体的な受験資格、出題内容まで、受験生が知りたい情報を網羅的にまとめました。
理学療法士を目指す上で、どのくらいのレベルが求められるのか、試験の概要を正確に理解するための内容となっています。
理学療法士国家試験とは?まずは概要をチェック
理学療法士国家試験は、「理学療法士及び作業療法士法」に基づき、理学療法士として業務を行うために必要な知識を評価する国の検定試験です。
正式名称は「理学療法士国家試験」であり、この試験に合格し、免許登録をすることで初めて理学療法士として働くことが可能になります。
年に一度実施され、試験の日程や受験資格、出題範囲などの詳細は厚生労働省から発表されます。
試験日程と申し込み方法
理学療法士国家試験は、例年2月に実施されます。直近の第59回試験は2024年2月18日に行われました。第60回試験は2025年2月に、第61回試験は2026年2月23日(月)に実施される予定です。
試験会場は北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県、沖縄県に設置されるのが通例です。受験の申し込み期間は、第61回試験の場合、2025年12月15日(月)から2026年1月5日(月)とされています。受験願書などの必要書類を受付期間内に提出する必要があります。
試験当日は時間に余裕を持って会場に到着し、トイレの場所などを事前に確認しておくと落ち着いて試験に臨めます。(当校では最寄り駅に毎年8:30に集合して遅刻を防止、教員が激励の挨拶をして送り出します)
受験資格を得るための3つのルート
理学療法士国家試験の受験資格を得るためには、主に3つのルートがあります。
1. **文部科学大臣または都道府県知事が指定した養成校を卒業するルート**: 高校卒業後、文部科学大臣または都道府県知事が指定する理学療法士養成施設で4年制または3年制の専門課程を修了し、卒業する(または卒業見込みである)ことが最も一般的なルートです。
2. **海外で理学療法に関する教育を修了し、厚生労働大臣の認定を受けるルート**: 海外の理学療法に関する学校や施設を卒業し、日本の理学療法士と同等以上の知識および技能を有すると厚生労働大臣から認定を受ける方法です。
3. **特定の経過措置によるルート**: 昭和40年8月28日時点で、文部大臣または厚生大臣指定の学校または施設において、理学療法士となるのに必要な知識および技能の修得を終えているか、または修業中であり、この法律の施行後にその修得を終えた者も受験資格を得ることができます。
出題範囲と問題形式の詳細
試験はマークシート方式の筆記試験のみで、実技試験や口述試験はありません。
問題は午前と午後に分かれ、一般問題と実地問題から構成されます。
総問題数は200問で、配点は一般問題が1問1点、実地問題が1問3点、合計280点満点です。
出題範囲は、解剖学、生理学、運動学といった基礎医学分野から、臨床医学、臨床心理学、リハビリテーション医学、人間発達学、理学療法といった専門分野まで多岐にわたります。
筋肉や骨の構造、てこや嚥下の原理など、基礎的な知識が臨床場面でどのように応用されるかが問われます。
発達に応じた体操など、幅広い教科の知識が求められ、一部の基礎医学問題は作業療法士と共通です。
気になる理学療法士国家試験の難易度は?合格率の推移から解説
理学療法士国家試験の難易度は、合格率の高さから比較的易しいと誤解されがちですが、専門的な知識が問われるため、決して簡単な試験ではありません。
合格率の数字だけでは、その難しさを正確に測ることは困難です。
偏差値で示されるものではなく、養成校での学習の質が合否に直結します。到達度試験なので280点満点中6割の168点以上得点した場合は全員合格します。ここでは、最新のデータや過去の合格率の推移、出題傾向から試験の本当の難易度を解説します。
最新の理学療法士国家試験の合格率
2024年3月に発表された第59回理学療法士国家試験(令和6年実施)の結果では、受験者数12,629人に対し、合格者数11,282人で、合格率は89.3%でした。このうち、新卒者の合格率は95.3%と非常に高い水準です。
第58回試験(2023年実施)の合格率は87.4%であり、近年は80%台後半で安定した合格率を維持しています。この数字は、養成校での教育課程を真面目に修了すれば、多くの人が合格できるレベルであることを示しています。しかし、これは十分な試験対策を行った結果であり、油断はできません。
過去6年間の合格率の動向
過去6年間の合格率を見ると、第55回(2020年)が86.4%、第56回(2021年)が79.0%、第57回(2022年)が79.6%、第58回(2023年・令和5年)が87.4%、そして最新の第59回(2024年)が87.1%という動向です。
2021年と2022年には合格率が80%を下回り
ましたが、その後は回復傾向にあります。
過去には第49回試験のように合格率が大きく変動することもあり、試験の難易度には波があることがわかります。この推移から、常に安定して高い合格率が保証されているわけではなく、年度ごとの傾向を把握し、着実な準備が求められることが読み取れます。
合格率だけでは判断できない?養成校での学習が重要
理学療法士国家試験の高い合格率は、受験資格を得るまでの養成校における3〜4年間の教育課程の成果です。
学生は解剖学や生理学といった基礎から、専門的な理学療法の知識・技術までを体系的に学び、臨床実習を通じて実践力を養います。
このカリキュラム自体が国家試験に向けた土台作りとなっており、日々の授業や実習への取り組みが合否に大きく影響します。
そのため、合格率の数字だけを見て試験の難易度を判断するのではなく、養成校での学習の積み重ねこそが最も重要であると認識する必要があります。
合格は、長期間にわたる地道な努力の結果と言えます。
合格を掴むための国家試験対策と具体的な勉強法
理学療法士国家試験の合格には、戦略的な対策と効率的な勉強法が不可欠です。
試験の概要や難易度を把握した上で、具体的な学習計画を立てることが重要になります。
このセクションでは、厚生労働省が公開する過去問の活用法から、専門分野と共通分野それぞれに適した勉強のアプローチ、さらにはスキマ時間を有効に使うためのツール選びまで、合格を確実にするための実践的な方法を解説します。
厚生労働省の過去問を活用した実践的な対策法
最も効果的な試験対策は、厚生労働省のウェブサイトで公開されている過去問を繰り返し解くことです。
過去問に取り組むことで、出題形式、問題の難易度、そして時間配分に慣れることができます。
特に、実際の臨床場面を想定した実地問題は、知識の応用力が問われるため、重点的な対策が欠かせません。
ただ問題を解いて答え合わせをするだけでなく、なぜその選択肢が正解で、他の選択肢がなぜ誤りなのかを一つひとつ徹底的に分析することが重要です。
このプロセスを通じて、断片的な知識が体系化され、真の実力が身につきます。
専門分野・共通分野別のおすすめ勉強法
効率的に学習を進めるには、分野ごとの特性に合わせた勉強法が求められます。
解剖学や生理学、運動学といった共通分野は、すべての専門分野の土台となるため、早い段階から図やイラストを活用して視覚的に理解を深め、完璧に固めておくことが重要です。
一方、運動療法や理学療法評価学などの専門分野は、臨床実習で経験した症例と関連付けて学習すると、知識が定着しやすくなります。
疾患の病態と具体的なアプローチをセットで覚えることで、応用力が養われます。
まずは得点源にしやすい共通分野を固め、そこから専門分野へと学習範囲を広げていく計画的なアプローチが有効です。
スキマ時間を有効活用できるアプリや参考書の選び方
通学中や休憩時間などのスキマ時間を活用することは、国家試験対策において非常に重要です。
一問一答形式のスマートフォンアプリや、要点がまとめられた学習サイトは、知識の反復学習や暗記に適しています。
参考書を選ぶ際は、自分の学習レベルに合っており、図や表が多くて視覚的に理解しやすいものを選ぶと良いでしょう。
また、予備校が作成した予想問題や、合格者の学習記録をまとめたnoteなども参考になります。当校ん本リハビリテーション専門学校では国試対策特別チームで良質な参考書を選択し、2026年からは新たに国試対策学習リコメンドシステム「KEISHIN.net」を導入いたします。
特に試験直前期には、新しい知識を詰め込むよりも、これらのツールを使って既習範囲の最終確認を行い、知識の精度を高めることが効果的です。
試験合格後の流れ|免許申請から理学療法士になるまで
国家試験の合格は理学療法士としてのキャリアの始まりに過ぎません。
合格後には、正式に理学療法士として働くための手続きが待っています。
このセクションでは、合格発表の確認方法から、免許を申請する際の具体的な手順、そして就職先に提出が必要な書類の準備まで、試験合格後から理学療法士としての一歩を踏み出すまでの流れを時系列で分かりやすく解説します。
合格発表の日程と確認方法
合格発表は、例年試験日から約1ヶ月後の3月下旬に行われます。
正式な発表日になると、厚生労働省のウェブサイトに合格者の受験地と受験番号が掲載されるため、オンラインで確認するのが一般的です。
合格者に対して個別に合格証書などの通知が郵送されるわけではないので注意が必要です。
ただし、成績および合否については、後日、受験者全員に書面で通知されます。
発表当日はサイトへのアクセスが集中して繋がりにくくなる可能性があるため、少し時間を置いてから確認することをおすすめします。
理学療法士免許の申請に必要な書類と手続き
国家試験合格後、理学療法士として業務を行うには免許申請の手続きが必須です。
この手続きには、いくつかの必要書類を揃えなければなりません。
具体的には、免許申請書、戸籍抄本または住民票の写し(発行後6ヶ月以内)、そして医師が発行した健康診断書が必要です。
また、登録免許税として9,000円分の収入印紙を購入し、申請書に貼付します。
養成校の卒業証明書の提出も求められる場合があります。
これらの提出書類一式を、住所地の保健所(一部地域では県庁)へ持参し、免許申請を行います。
就職先に提出する書類の準備
免許申請の手続きと並行して、内定している就職先への書類提出も進めましょう。
多くの医療機関や施設では、入職にあたり卒業証明書や成績証明書の提出が求められます。
また、理学療法士免許を取得した証明として、免許証のコピーの提出も必要です。
免許証は申請から手元に届くまで2〜3ヶ月かかる場合があります。それまでに勤務が始まる場合は、免許申請時に発行される「登録済証明書」を提出することで対応できます。登録済証明書は、オンライン申請を利用すると比較的早く取得できる場合があります(例えば、千葉市では申請時に希望すれば1〜2ヶ月ほどで郵送されるとされています)。
入職手続きを円滑に進めるため、履歴書の更新を含め、必要な書類を早めに準備し、提出期限を確認しておくことが大切です。
理学療法士国家試験に関するよくある質問
理学療法士国家試験を受験するにあたり、多くの人が共通の疑問や不安を抱えています。
例えば、社会人として働きながら合格を目指すことは可能なのか、万が一試験に不合格だった場合どうなるのか、また新卒と既卒では合格率にどの程度の差があるのかといった点です。
ここでは、そうしたよくある質問に対して、具体的かつ簡潔に回答していきます。
働きながら理学療法士国家試験の合格を目指せますか?
可能です。ただし、仕事と両立しながら学習時間を確保することが最大の課題となります。
通勤時間や休日などのスキマ時間を効率的に活用し、綿密な学習計画を立てることが不可欠です。独学での合格が難しい場合は、社会人向けの夜間部を設置している養成校や、サポートが充実した通信講座の利用も有効な選択肢となります。
もし国家試験に落ちたらどうなりますか?
国家試験に不合格となった場合、その年は理学療法士として働くことができず、翌年以降の試験に再挑戦することになります。
就職の内定を得ていた場合、内定取り消しとなる医療機関がある一方で、介護職として契約職員での雇用継続や、リハビリ助手としての採用を提案するケースも一部には存在します。諦めずに挑戦を続けることが大切です。
新卒と既卒で合格率に違いはありますか?
はい、合格率には顕著な差が見られます。
例年、新卒者の合格率が90%を超える高い水準であるのに対し、既卒者の合格率はそれを大幅に下回る傾向にあります。
これは、学習に専念できる環境を維持することの難しさや、モチベーションの維持が課題となるためです。
そのため、可能な限り現役での一発合格を目指すことが重要になります。
まとめ
本記事では、理学療法士国家試験の概要について、合格率や難易度、受験資格、出題内容などの観点から解説しました。
合格率は比較的高く推移していますが、それは養成校での3〜4年間にわたる体系的な学習と実習の積み重ねが前提となっています。
試験に合格するためには、まず試験の全体像を正確に把握し、厚生労働省が公開する過去問を中心に、計画的な対策を進めることが不可欠です。
また、試験合格後には免許申請という重要な手続きが控えています。
このまとめを参考に、試験に関する正しい情報を得て、理学療法士になるための着実な一歩を踏み出してください。
監修:日本リハビリテーション専門学校 鍋城武志(理学療法士)