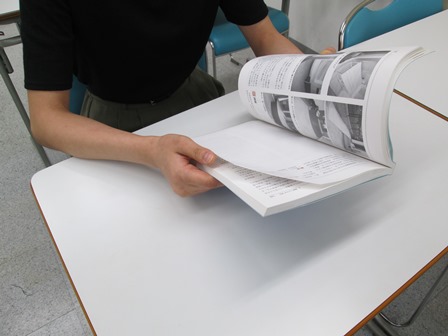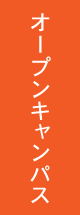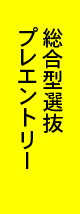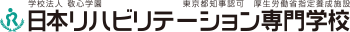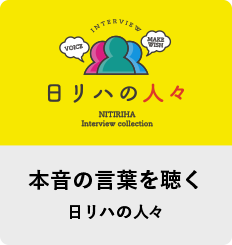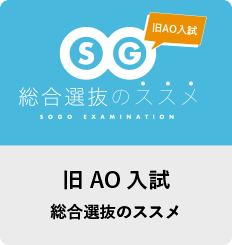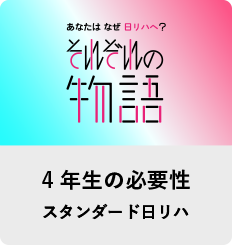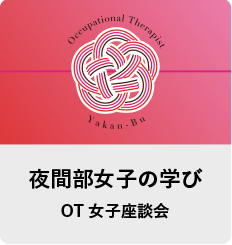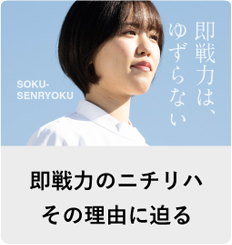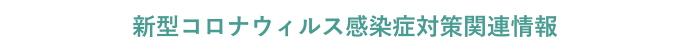作業療法学科昼間部1年生は、6月から7月にかけて、5週間にわたり、毎週水曜日、計5日間、同じ学生が同じ施設に通い、ボランティア活動を体験しました。「体験実習」という新しい授業での学外実習です。
今年の作業療法学科1年生は、ほとんどが高校を卒業してすぐに入学してきました。医療や福祉の現場を見た経験も少なく、身近に高齢者や障がい者の方がいない人も多いのが現状です。
これからリハビリテーションや作業療法を学んでいくのですが、そもそも、高齢者や障がい者の方々と接したことが少ないのです。なので、仕事のイメージがつかないだけでなく、お年寄りや障がい者の方々とどのようにお話をしたら良いかわからないという学生が多いのです。
作業療法士は、対象者の方とコミュニケーションを取りながらリハビリテーションを進めていくことが求められます。そのためには、知識や技術を学ぶと同時に、お年寄りや障がい者の方々と関わり、寄り添いながらお話をする経験が大切だと考えています。
作業療法学科昼間部1年生のボランティア体験実習は、できるだけ早く、学生が臨床の場でこのような経験を積み、知識・技術だけではない、人と人との血の通った交流ができる人に成長してもらいたいというねらいがあるのです。
さて、計5日間のボランティア体験は学生にとってどのようなものだったのでしょう?「楽しい」という声も多かったのですが、同時に、「話が続かない」とか「何を話していいかわからない」という戸惑いの声も多く聞かれました。世代の違う若者とお年寄り同士では、共通の話題がなかなか見つからないのでしょう。
しかし、「次回までに昔の歌を覚えよう」とか「釣りの勉強をしていこう」とか「将棋を覚えよう」など、お年寄りの世界に近づこうと努力する姿が見られ、頼もしく思いました。誰から指示されなくても、自発的に、自分にできることに一生懸命取り組もうという姿勢が現れていました。

全ての体験実習が終わり、7月20日にセミナーを行いました。学生が小グループに分かれて、自分たちの体験内容やそこで学んだことを発表し合う会です。別科目の「情報科学」の授業の中で学んだ「パワーポイント」を駆使し、イラストや動画が入った、カラフルで、とてもわかりやすい発表がたくさんありました。ここでも、知識や技術はただ受け身的に学ぶのではなく、使う場があってこそ身につくものだと思いました。

これから、この学生たちがどのように成長していくのか本当に楽しみです。
今回のボランティア体験実習では、20を超える施設にご協力頂きました。最後に学生に貴重な経験の場を与えて下さった、利用者の皆さま、施設の職員の皆さまに心から感謝申し上げます。
今回のボランティア実習にご協力いただいた施設(五十音順)
あい介護老人保健施設
介護老人保健施設足立老人ケアセンター
介護老人保健施設あんず苑
介護老人保健施設エンジェルコート
介護老人保健施設小金井あんず苑
介護老人保健施設ハートケア流山
介護老人保健施設フォレスト西早稲田
介護老人保健施設ふれあいの里
介護老人保健施設みかじま
介護老人保健施設みぬま
高齢者在宅サービスセンター西新井
デイサービスセンターさや
デイステーション涼風
東京総合保健福祉センター江古田の森デイサービスセンター江古田の森
特別養護老人ホーム金井原苑
錦クリニック デイケアセンター
ニチイホーム下丸子
三鷹市高齢者センターけやき苑
有料老人ホームサンライズヴィラ海老名
陽和病院
よりあいデイ・つくし
老人保健施設ビバ・フローラ