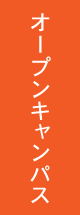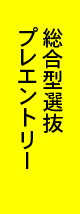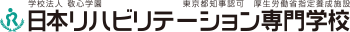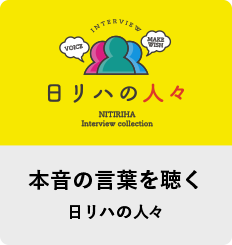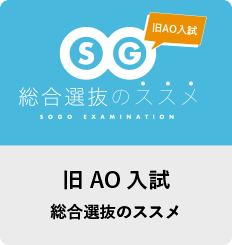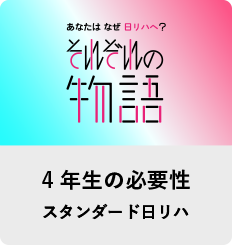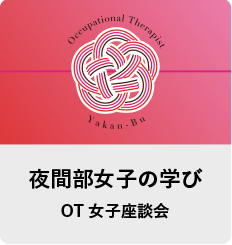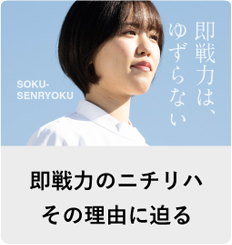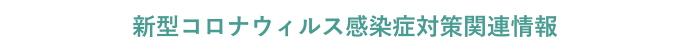作業療法学科夜間部教員の山田です。今回は「occupy」についてお話しさせていただきたいと思います。
作業療法は「occupational therapy」の日本語訳です。「occupational」の動詞形である「occupy」の意味のひとつに「占める」という訳があります。そのヒトの人生や時間を「占める」といったように使われます。
僕の生活にはありがたいことに1人の時間があります。その時間を様々なことに費やしておりますが、趣味の1つとしてヨガを実践しております。

ヨガの歴史は古く、紀元前2500年前までさかのぼると言われています。さらにヨガ・スートラという経典によりヨガが体系化されたのが2~4世紀ごろです。
「出尽くした」といわれるくらい次々に新しいものが生み出されている現代でも
実践され続けているというところに、まず僕は強い関心を持ちました。
また、ヨガには筋トレやストレッチなどの運動要素の他に、心を落ち着かせたり、自身の内面を見つめ直したりといった精神心理的な要素、さらにはどのように生きるべきかといった人生哲学のようなものも含まれています。
「こころとからだのリハビリテーション」である作業療法士につながるものを感じたのです。
作業療法では、生活時間を複数の作業が「占める」ことによってヒトの生活が成り立っていると考えます。そして、作業は「セルフケア」「仕事」「遊び」と大きく分けられ、このバランスが崩れるとヒトはうまく生きられなくなります。
僕にとってのヨガは「遊び」に入り、こころをリセットする手段の一つとして生活に潤いを与えている「大切な作業」です。
僕自身の「occupy」の話でした。