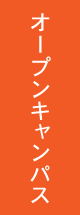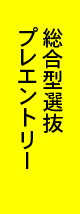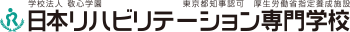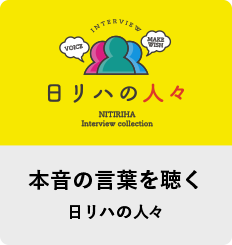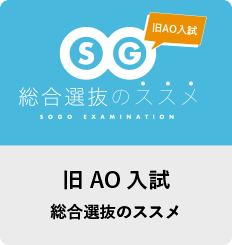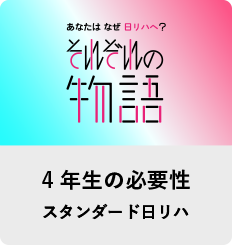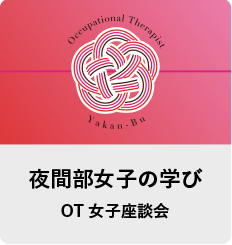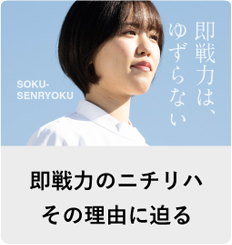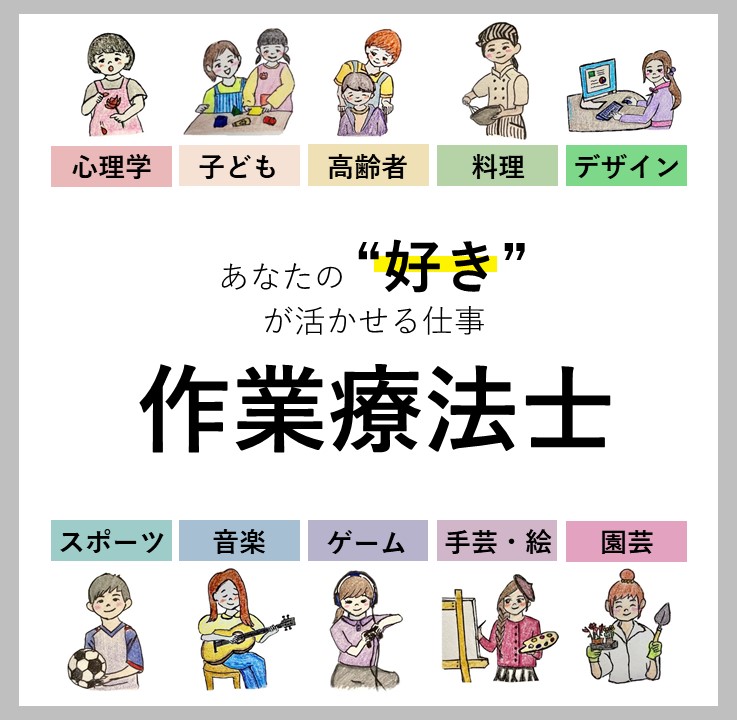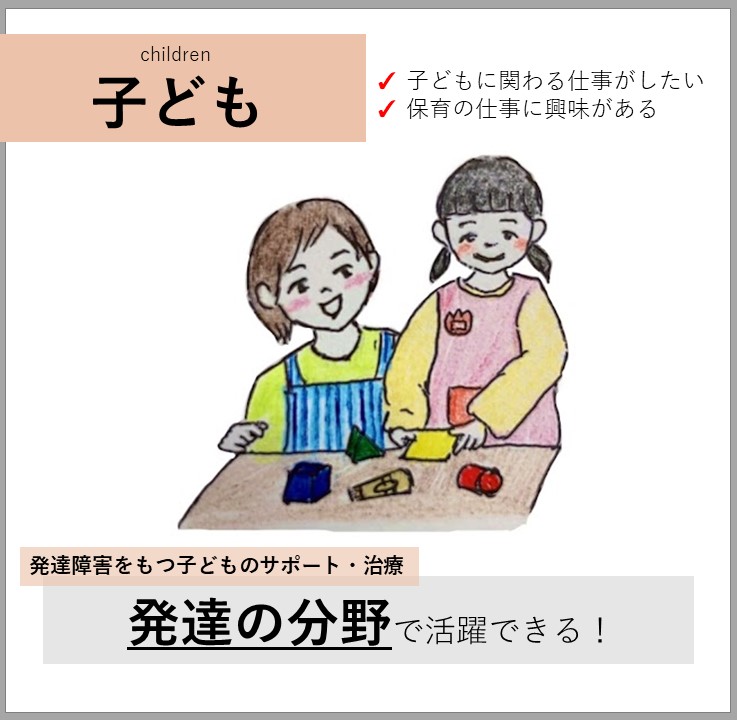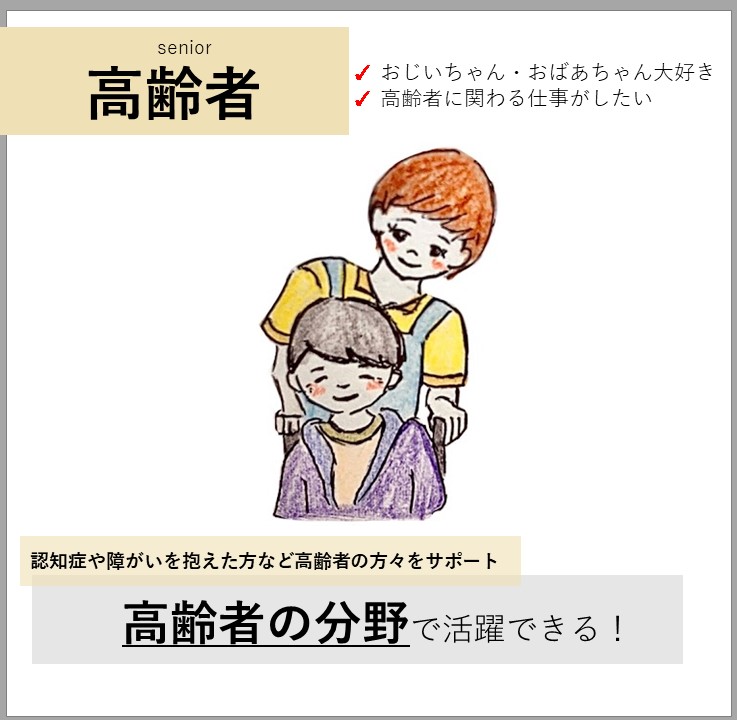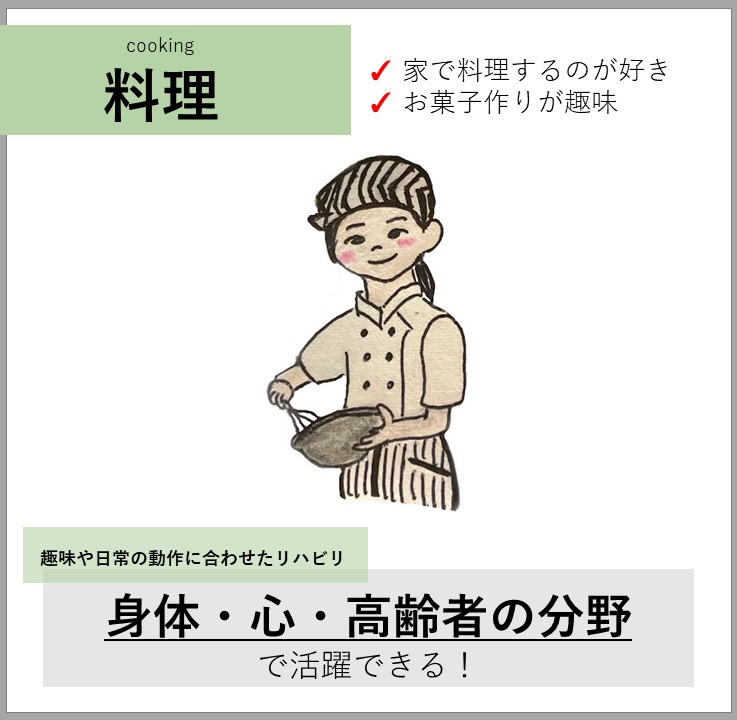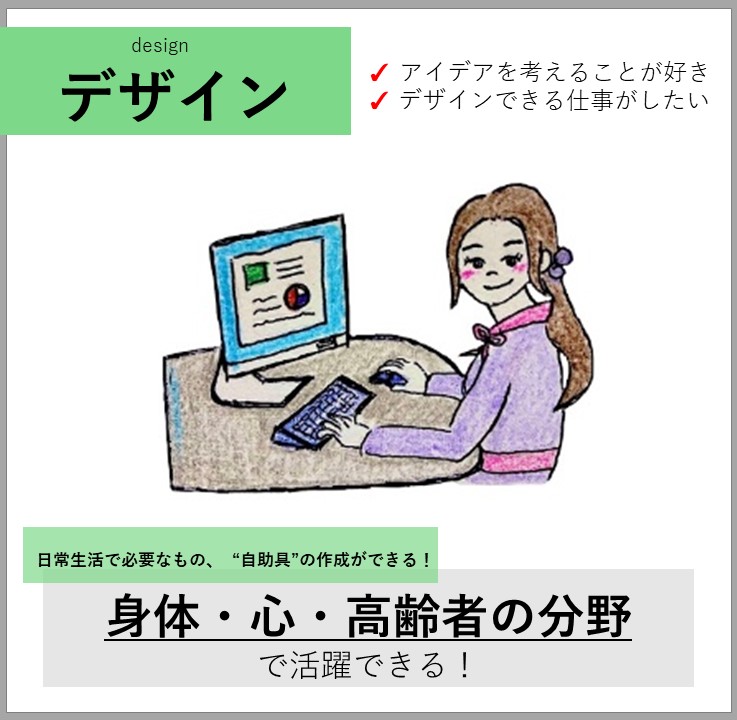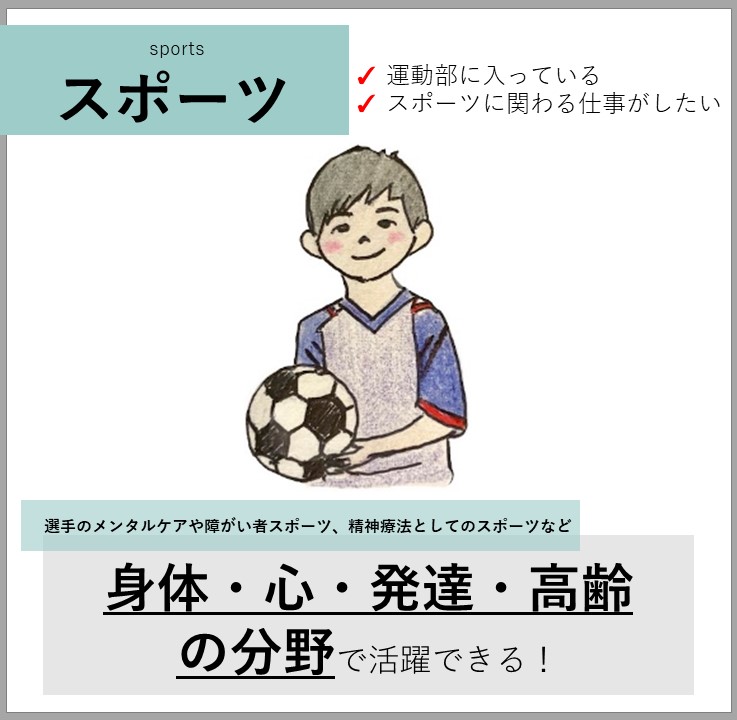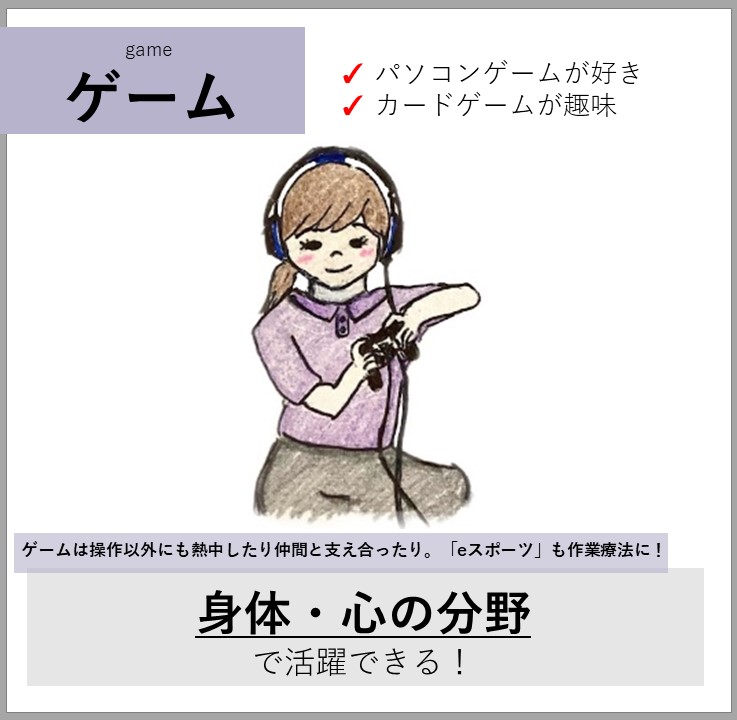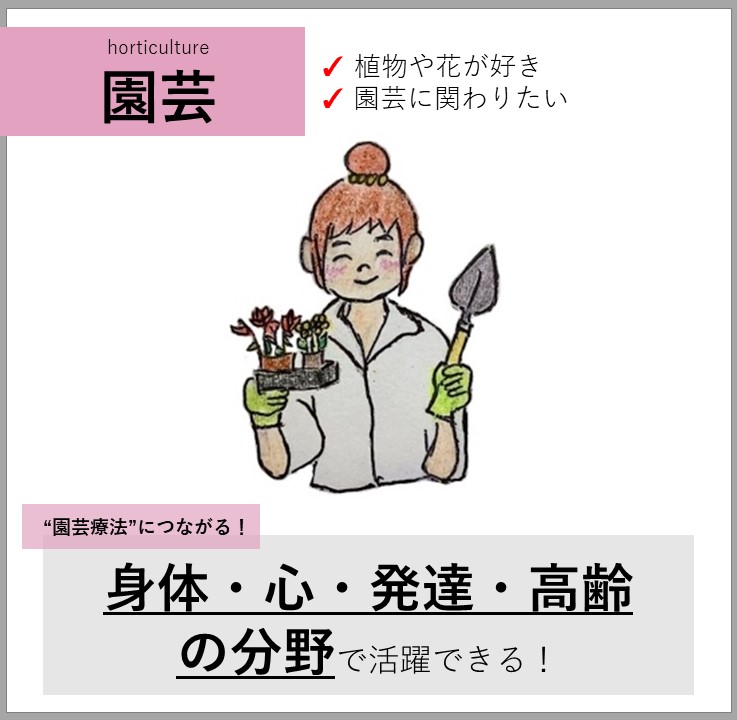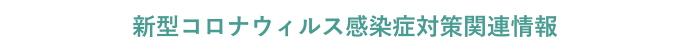理学療法士・作業療法士フルタイム勤務の課題
中央社会保険医療協議会 総会(第378回)で課題に挙げられたのは、リハビリ専門職の常勤要件の取扱いについてです。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の女性割合は、それぞれ約4割、約6割、約8割にまで上ります。リハビリ専門職の人数増加と共に、女性のフルタイム勤務者も増えています。
リハビリ専門職は女性の割合が多いことや、医師の指示の下で専門性の高い医療を提供していることを踏まえ、女性がより働きやすい環境になるよう、働き方改革が今回の会議で推進されました。
具体的には、以下の2点から生まれる「子供がいる女性がフルタイム勤務できない」という現状を改善する必要があります。
・リハビリテーションに関する診療報酬項目には、リハビリ専門職の専従・常勤配置等が施設基準の要件となっているものがある。
・育児・介護休業法において、3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置(1日原則6時間)が義務づけられている。
多様な働き方に合わせた改善案

前述の課題に対して、今回の会議で改善案が出されました。リハビリ専門職の常勤要件の取扱いを変更しようというものです。
<リハビリ専門職の常勤要件の取扱い>
リハビリ専門職は女性の割合が多いことや、医師の指示の下で専門性の高い医療を提供していることを踏まえ、リハビリ専門職の専従・常勤配置等が要件となっている項目については、週一定時間の勤務を行っている複数の非常勤従事者の組み合わせにより、常勤配置されているものとみなしてはどうか。
<専従要件の取扱い>
医療従事者の専従要件については、より効率的な医療提供を可能とする観点から、
・業務内容の類似性や対象患者数に応じた弾力的な現行の運用や、
・医療資源の少ない地域において適用されている緩和措置
等を参考に、医療提供の質の確保に配慮しつつ、より弾力的な運用が可能となるよう必要な見直しを検討してはどうか。また、検討にあたっては、対象患者数が一定程度以下の場合や、当該業務を実施していない時間帯の取扱い等の視点で検討してはどうか。
つまり、子供がいる理学療法士・作業療法士が多い職場で、フルタイムの勤務が難しい場合であっても、複数のパートタイム勤務の方がいれば大丈夫なように要件を変えようという動きです。
「誰か1人がいなきゃいけないのに、子供がいるからできない」といった悩みは、多くの育児をしながら働く女性が持っています。これらを制度からサポートする動きが、リハビリ専門職では出てきています。
子育てをしながらリハビリ専門職として働くということ

これから理学療法士・作業療法士を目指す人は、「リハビリを行う仕事」と聞くと男性のイメージがあるという方も少なくありません。
しかし、実際は理学療法士は4割が女性・作業療法士は6割が女性であり、大きな男女の偏りがある仕事ではありません。また、男女で仕事内容に違いはなく、どちらも専門性の高い仕事ができます。女性は育児をしながら働く人が増えてきていますので、子どもがいる方でも働きやすいようにしていくことは医療業界全体の課題でもあります。
さらに、医療関係のどの職業もそうですが、女性の患者さんに対する気遣いというところで女性が対応した方がよりよいケースもあります。女性の理学療法士・作業療法士が担当することができると、女性の患者さんにとっては安心感が生まれやすくなるようです。
このように、リハビリテーションの世界では、女性の理学療法士・作業療法士の存在はとても大切です。働きながら育児や家事をする女性が増えている現在、それをサポートできるような制度変更が進めることは必要でしょう。
こちらの記事もおすすめです
「2つの医療系国家資格、理学療法士と看護師の違いとは?2040年に最も求められる職業」