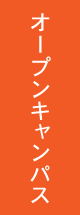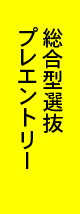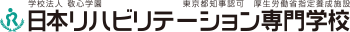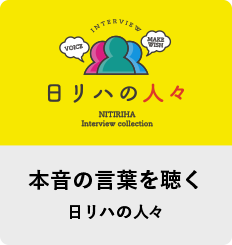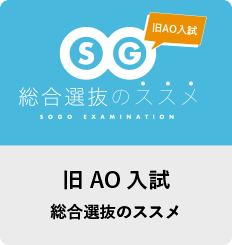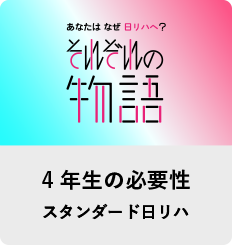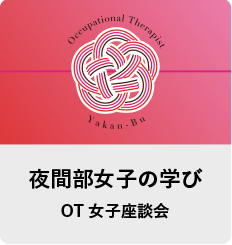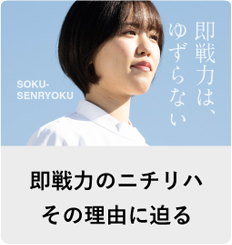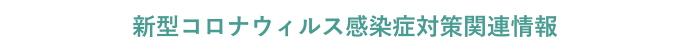作業療法士の療育での役割とは?発達障害への関わりや仕事内容、理学療法士との違い
監修:日本リハビリテーション専門学校 田中 克一(作業療法士)
療育における作業療法士とは、子どもの心と身体の発達を支援する専門職です。
その仕事内容は、日常生活の動作訓練から遊びを通じた感覚機能の向上まで多岐にわたります。
特に発達障害のある子どもに対して、その子に合った方法で社会生活への適応をサポートします。
本記事では、作業療法士の具体的な役割や、混同されやすい理学療法士との仕事内容の違いについても詳しく解説します。
療育分野で活躍する作業療法士(OT)とは?
療育分野における作業療法士(OT)は、身体や心に障害のある子どもや、発達に特性のある子どもを対象に、日常生活や遊びなどの「作業」活動を通して支援する専門家です。
OTはOccupational Therapistの略称で、食事や着替えといった身の回りの動作から、学習や人との関わりに至るまで、子どもが自分らしく生活できるようサポートします。
特に子どもの発達段階に合わせて、その子に必要なスキルが身につくよう、専門的な視点からアプローチを行うのが特徴です。
【具体的な仕事内容】作業療法士が療育で担う4つの役割
作業療法士は療育の現場で、子どもの発達段階や特性に応じた多岐にわたる支援を担います。
その役割は、単に身体機能の訓練を行うだけでなく、日常生活の自立、感覚機能の発達、学習や社会性の基盤づくりまで及びます。
ここでは、作業療法士が療育で担う具体的な4つの役割について、それぞれ詳しく解説します。
日常生活動作(食事・着替えなど)の自立をサポート
作業療法士は、子どもが日常生活を送る上で必要となる基本的な動作の自立を支援します。
例えば、スプーンやフォークを上手に使って食事をする、ボタンのかけ外しや服の着脱を一人で行う、トイレトレーニングを進めるなど、具体的な動作の練習を行います。
特に幼児期の子どもに対しては、それぞれの発達段階に合わせて、道具の選び方や使い方、動作の手順などを丁寧に指導します。
単にやり方を教えるだけでなく、子どもが「自分でできた」という達成感を得られるよう、意欲を引き出す工夫をしながら関わることが重要です。
こうした支援を通じて、子どもの自信と自立心を育みます。
遊びを通じた感覚統合の発達支援
作業療法士は、遊びを通して子どもの感覚統合を促す支援を行います。
感覚統合とは、触覚、固有覚、前庭覚といったさまざまな感覚を脳内で整理し、状況に応じて適切に反応する力のことです。
例えば、ブランコに乗って揺れを感じたり、ボールプールで身体を動かしたり、粘土で遊んだりといった活動を通じて、感覚の偏りを調整します。
特に自閉症スペクトラム症の子どもに見られる、感覚の過敏さや鈍感さに対して、その子に合った遊びを提供し、脳機能の発達をサポートします。
楽しみながら取り組める活動の中で、身体の動かし方や力加減を学び、情緒の安定を図ります。
手先の器用さ(微細運動)を高める訓練
作業療法士は、手や指先を使った細かな動き、いわゆる「微細運動」能力を高める訓練を行います。
この能力は、文字を書いたり、絵を描いたり、ハサミを使ったり、紐を結んだりと、日常生活や学習のあらゆる場面で必要とされます。
訓練では、ビーズ通しや粘土遊び、折り紙、パズルなど、子どもの興味関心に合わせて楽しみながら取り組める課題を用います。
手と目の協応動作を促し、指先の力加減や巧みな動きを育むことで、身の回りのことを自分で行う力や、就学後の学習活動の土台を築きます。
個々の発達レベルに応じた運動課題を設定し、成功体験を積み重ねられるよう支援します。
学習や社会性を育むための環境調整と保護者支援
作業療法士の役割は、子どもへの直接的な訓練だけではありません。
子どもが園や学校などの集団生活にスムーズに適応できるよう、環境を調整することも重要な仕事です。
例えば、集中しやすいように椅子の高さや机の配置を工夫したり、読みやすいフォントの教材を提案したりします。
また、保護者との連携も不可欠であり、家庭での子どもの様子を聞き取り、療育での目標を共有します。
日々の関わり方や声かけの方法など、具体的な相談に応じ、専門的な視点から助言を行うことで、保護者の不安を軽減し、家庭と療育施設が一体となって子どもの成長を支える体制を築きます。
理学療法士(PT)や言語聴覚士(ST)との役割の違いを解説
療育の現場では、作業療法士(OT)の他に、理学療法士(PT)や言語聴覚士(ST)といった専門職が連携して子どもを支援します。
これらの職種は「リハビリテーション職」と総称されますが、それぞれに専門分野が異なります。
作業療法士の役割をより深く理解するために、ここでは理学療法や言語聴覚の専門家との役割の違いについて解説します。
作業療法士(OT):応用的な動作や心のケアを担当
作業療法士(OT)は、食事や着替え、遊び、学習など、人が生活する上で行うあらゆる「作業」を通して、心と身体の両面から支援する専門職です。
基本的な動作が可能になった上で、それらを応用して日常生活や社会生活を円滑に送れるように働きかけます。
例えば、手先を使った細かな作業の練習や、集団活動への参加を促す支援がこれにあたります。
また、精神障害領域での経験も活かされ、子どもの精神的な安定や自己肯定感を育むための関わりも重視します。
対象となる活動が広範で、その子の生活全体を捉えた支援を行うのが特徴です。
理学療法士(PT):基本的な動作(座る・立つ・歩く)の専門家
理学療法士(PT)は、寝返る、起き上がる、座る、立つ、歩くといった、生活の基本となる動作機能(粗大運動)の専門家です。
病気やケガ、障害によって身体機能が低下した人に対して、運動療法や物理療法(電気刺激など)を用いて機能の回復や維持を図ります。
療育分野では、主に脳性麻痺など身体に障害のある子どもを対象に、関節の動きを広げたり、筋力をつけたりする訓練を行います。
作業療法士が応用的な動作を支援するのに対し、理学療法士はその土台となる基本的な身体機能の向上を目指す役割を担います。
言語聴覚士(ST):コミュニケーションや食事の専門家
言語聴覚士(ST)は、「話す」「聞く」「表現する」といったコミュニケーション機能や、「食べる」「飲み込む」といった摂食嚥下機能に問題がある人を支援する専門家です。
療育分野では、言葉の発達に遅れがある子どもや、発音に課題がある子どもに対して、個別の訓練や指導を行います。
また、食べ物をうまく噛めない、飲み込めないといった食事の問題にも対応し、安全でおいしく食事ができるようサポートします。
言葉やコミュニケーション、食事といった特定の領域に特化して、専門的なアプローチを行うのが言語聴覚士の役割です。
作業療法士が療育分野で活躍できる主な職場
作業療法士が療育の専門性を発揮できる職場は、従来の医療機関だけでなく、児童福祉の分野にも大きく広がっています。子どもの発達支援に対する社会的なニーズの高まりとともに、多様な施設で作業療法士の力が求められています。
ここでは、療育分野で活躍できる主な職場と、それぞれの特徴を解説します。
児童発達支援センター・事業所
児童発達支援センターや事業所は、主に障害のある未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う通所施設です。
作業療法士は、個別または小集団での療育プログラムを担当し、一人ひとりの発達課題に合わせた支援を計画・実行します。
特に地域の児童発達支援の中核を担う療育センターでは、他の事業所への助言や保育所等訪問支援など、より幅広い役割を担うこともあります。
子どもの早期発達支援に深く関わることができる代表的な職場です。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、障害のある就学児(小学生から高校生)を対象に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などを行う施設です。
学習支援や創作活動、運動プログラムなどを提供し、学童保育(アフタースクール)のような役割も担います。
作業療法士は、ソーシャルスキルトレーニングや学習につまずきのある子どもへの支援、身体を使った遊びなどを通じて、子どもたちの自己肯定感や社会性を育む役割を担います。
学齢期の子どもの成長を支える重要な職場です。
病院の小児科やリハビリテーション科
大学病院や地域の総合病院などに設置されている小児科やリハビリテーション科も、作業療法士が療育に関わる重要な職場です。
こちらでは、脳性麻痺や先天性の疾患、事故による後遺症など、医学的な管理が必要な子どもを対象としたリハビリテーションが中心となります。
医師や看護師、理学療法士、言語聴覚士など、他の医療専門職と緊密に連携しながら、治療の一環として作業療法を提供します。
医療的な視点から子どもの発達を支援する専門性が求められる職場です。
療育分野で作業療法士として働くメリット
療育分野は、作業療法士にとって大きなやりがいと専門性の発揮が期待できる領域です。
病院などの医療機関とは異なる環境で働くことには、多くの魅力があります。
ここでは、作業療法士が療育分野で働くことの具体的なメリットを3つの視点から解説します。
子どもの成長を長期的に見守れるやりがいがある
療育施設では、一人の子どもと数ヶ月から数年にわたって継続的に関わることが一般的です。
例えば3年といった長いスパンで関わる中で、昨日までできなかったことが今日できるようになる、という成長の瞬間に何度も立ち会うことができます。
急性期の病院のように短期間で担当が変わることが少ないため、子どもの小さな変化や成長を間近で実感し、その喜びを保護者と分かち合えることは、この仕事ならではの大きなやりがいとなります。
長期的な視点でじっくりと子どもと向き合いたい人にとって、非常に魅力的な環境です。
保護者と密接に関わりながら支援できる
療育分野では、子ども本人への支援と同じくらい、保護者との連携が重要視されます。
日々の送迎時や面談を通じて、家庭での様子を共有したり、子育ての悩みや不安について相談に乗ったりする機会が多くあります。
療育での取り組みを家庭でも実践してもらうなど、保護者と二人三脚で子どもの成長を支えていくプロセスは、深い信頼関係を築くことにつながります。
子どもの成長を共に喜び、保護者からも感謝される経験は、専門職としての満足感を高めるでしょう。
子どもだけでなく、その家族全体をサポートすることにやりがいを感じる人に向いています。
多様な働き方を選びやすい
療育分野の職場は、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなど、全国的に施設数が増加しており、求人も豊富にあります。
そのため、自分のライフスタイルに合った働き方を選びやすいのがメリットです。
正社員としての勤務はもちろん、パートタイムや非常勤として働く選択肢も多く、家庭との両立もしやすい傾向にあります。
また、施設によって提供するプログラムや特色が異なるため、自分の興味や専門性を活かせる職場を見つけやすいでしょう。
キャリアプランに合わせて柔軟な働き方を選択できる点は、大きな魅力の一つです。
療育分野で働く際に知っておきたいこと
療育分野はやりがいが大きい一方で、医療機関での勤務とは異なる側面もあります。
転職や就職を考える際には、メリットだけでなく、事前に知っておくべき現実的な情報も理解しておくことが大切です。
ここでは、給与や休日、求められるスキルなど、療育分野で働く上で留意しておきたいポイントを解説します。
病院勤務との給与や休日の違い
一般的に、福祉施設である療育施設の給与水準は、医療機関と比較するとやや低い傾向にある場合があります。
ただし、これは施設規模や運営母体によって大きく異なるため、一概には言えません。
一方で、多くの療育施設は日中の運営が基本であり、夜勤がないことがほとんどです。
また、カレンダー通りに土日祝日が休みとなる施設も多く、プライベートの時間を確保しやすいというメリットがあります。
給与だけでなく、年間休日数や福利厚生など、総合的な労働条件を比較検討して職場を選ぶ視点が求められます。
保護者との円滑なコミュニケーションの重要性
療育の効果を最大限に高めるためには、保護者との信頼関係の構築が不可欠です。
子どもは日々成長し変化するため、療育施設での様子をこまめに伝え、家庭での様子を丁寧にヒアリングすることが求められます。
時には、保護者が子どもの発達について不安や悩みを抱えている場面に立ち会うことも少なくありません。
専門的な知識を分かりやすく伝えるだけでなく、保護者の気持ちに寄り添い、共感する姿勢が重要になります。
子どもへの支援スキルと同様に、保護者との円滑なコミュニケーション能力が強く求められる分野です。
療育分野の作業療法士に向いている人の特徴
療育分野で作業療法士として活躍するためには、専門的な知識や技術はもちろんのこと、子どもやその家族と向き合う上での人間性や適性が重要になります。
ここでは、どのような人が療育分野の作業療法士に向いているのか、その特徴を3つのポイントに絞って解説します。
子どもの目線に立って根気強く関われる
子どもの発達は一直線に進むわけではなく、時には停滞したり後退したりすることもあります。
そのため、短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点で子どものペースに合わせて根気強く関わり続ける姿勢が不可欠です。
大人の都合や計画を押し付けるのではなく、子どもの興味や関心、その日のコンディションを尊重し、支援内容を柔軟に調整できることが求められます。
子どもの世界に入り込み、同じ目線で物事を考え、一緒に楽しむことができる人は、子どもとの信頼関係を築きやすいでしょう。
観察力があり、小さな変化に気づける
特に言葉での表現が難しい子どもと関わる場合、その子の行動や表情、しぐさなどから気持ちや状態を読み取る高い観察力が求められます。
子どもが発する非言語的なサインを見逃さず、「なぜ今この行動をとるのか」を考える洞察力が必要です。
昨日より少し長く椅子に座れた、苦手な食べ物を一口だけ口にできた、といった日々の小さな成長や変化に気づき、それを認め、褒めることで子どもの自己肯定感を育みます。
細やかな変化を見つけ、支援に活かせる人はこの分野で大きく貢献できます。
多職種と連携してチームで働くことが得意
療育は、作業療法士一人で行うものではなく、理学療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員、心理士など、さまざまな専門職が連携して行われます。
それぞれの専門性を尊重し、カンファレンスなどを通じて情報を共有し、チームとして一貫した方針のもとで子どもを支援していくことが重要です。
自分の意見を伝えるだけでなく、他の職種の意見にも耳を傾け、協力してより良い支援を追求する協調性が不可欠です。
チームの一員として、円滑なコミュニケーションを取りながら働くことが得意な人は、療育の現場で力を発揮できます。
療育の専門性を高めるためにおすすめの資格
作業療法士として療育分野でキャリアを積んでいく上で、国家資格に加えて関連する資格を取得することは、自身の専門性を高め、客観的に証明するために非常に有効です。
スキルアップやキャリアアップを目指す際に役立つ資格はいくつか存在します。
ここでは、療育の専門性を深めるためにおすすめの資格を3つ紹介します。
認定作業療法士
認定作業療法士は、一般社団法人日本作業療法士協会が認定する資格で、臨床・教育・研究・管理運営において一定水準以上の能力を持つと認められた上位資格です。
取得するためには、5年以上の実務経験や協会が指定する研修の修了など、一定の要件を満たす必要があります。
感覚統合療法に関する認定資格
感覚統合療法は、療育の現場で広く用いられるアプローチの一つであり、特に自閉症スペクトラム症の子どもへの支援において重要視されています。
日本感覚統合学会では、専門の講習会を受講し、試験に合格することで得られる認定資格制度を設けています。
この資格を取得することで、感覚統合に関する専門的な知識と技術を体系的に習得し、より質の高い療育を実践できるようになります。
感覚統合の視点から子どもを評価し、アプローチできる専門家は、多くの療育施設で求められています。
児童発達支援士
児童発達支援士は、一般社団法人人間力認定協会が認定する民間資格です。
発達障害に関する正しい知識を学び、適切な支援を提供できる人材の育成を目的としています。
作業療法士だけでなく、保育士や教員、保護者など、子どもに関わるさまざまな立場の人が取得しています。
この資格の学習を通じて、発達支援の全体像を広く理解し、医学的な視点だけでなく、教育や福祉の視点も取り入れた多角的な支援が可能になります。
自身の専門分野以外の知識を補い、視野を広げる上で役立つ資格です。
作業療法士の療育に関するよくある質問
療育分野への就職や転職を検討している作業療法士の方から寄せられる、よくある質問とその回答をまとめました。
未経験からの挑戦、給与水準、求められるスキルなど、多くの方が気になる点について解説します。
キャリアを考える上での参考にしてください。
Q. 子どもと関わる上で特に求められるスキルは何ですか?
専門知識に加え、子どもの目線に立って根気強く関われる姿勢や、言葉にならないサインを読み取る観察力が求められます。
保育園などとは異なり、個々の発達課題に合わせた関わりが必要です。
また、子どもの支援は保護者との連携が不可欠なため、信頼関係を築くための高いコミュニケーション能力も同様に重要となります。
まとめ
療育における作業療法士は、食事や着替えといった日常生活動作から、遊びを通じた感覚統合の促進、学習の土台作りまで、子どもの発達を多角的に支援する重要な役割を担います。
理学療法士や言語聴覚士、保育士などの多職種と連携し、チームで子どもとその家族を支えます。
職場は児童発達支援センターや放課後等デイサービスなど多岐にわたり、長期的に子どもの成長を見守れるやりがいがあります。
未経験からでも挑戦可能であり、認定作業療法士などの資格取得を通じて、さらに専門性を高めていくこともできる、将来性のある分野です。
監修:日本リハビリテーション専門学校 田中 克一(作業療法士)