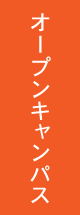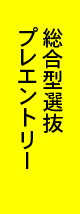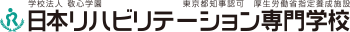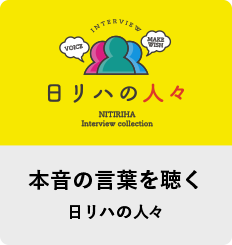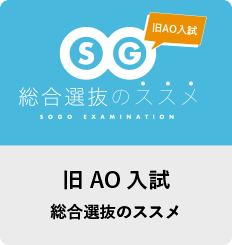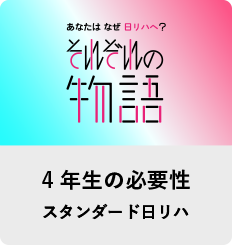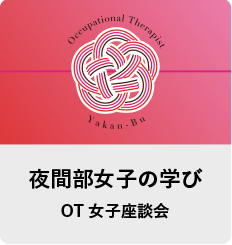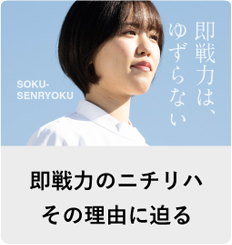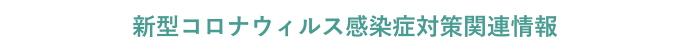作業療法学科夜間部教員の田中克一です。
私は作業療法士になる前は老人保健施設で介護の仕事をしていました。改めて介護職から作業療法士になってみて良かったことを振り返ってみたいと思います。
【良かったこと】
①心と身体の理解がかなり深まった!
OT養成校時代は解剖学、運動学、心理学、精神医学等の講義を通して身体と心の基礎について徹底的にたたき込まれました。
お陰で介助が必要なところ、要らないところの見極めができ、またより楽で利用者さんが安心できる介助や介助方法の提案ができるようになりました。また運動麻痺などの機能回復に関する介入についてもできるようになりました。
②給料が増えた!
介護職時代は夜勤してなんとか生活していました(夜勤手当がないと厳しい、、)。
作業療法士になって、その頃と比べて給料が増えたのは良かったです。確かに学費はかかりましたが長い人生を考えてあの時下した判断は間違えてなかったと思います。
③介護の頃と同じくらい笑顔に出会える!
介護職の頃は食事や入浴の介助の他にお花見に行ったり、街中のレストランに行ったりして、とても喜ばれたことを覚えています。
作業療法士になってからは一人で食事やお風呂に入れるようになって感謝していただくことが多くあります。
またお花見や外食の他、野菜を作ったり、料理をしたり、絵を描いたり、その人がやりたいことをを通して喜びや生きがいを感じてもらいます。そのような時の笑顔は本当に忘れられません。
作業療法士に興味のある方は当校に入学してお会いできれば幸いです。
社会人入試・オンライン入試は3月頭までですよ!