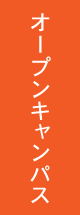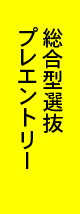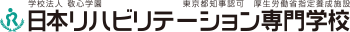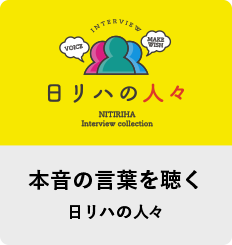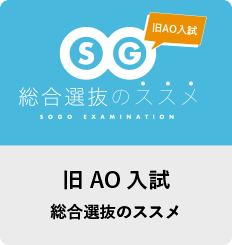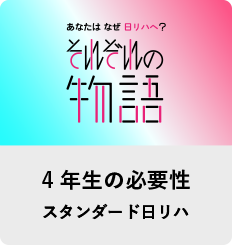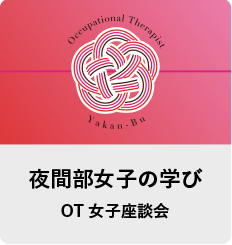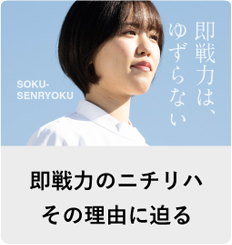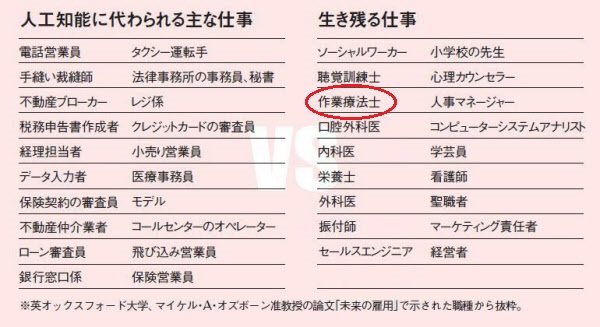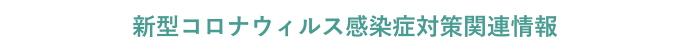こんにちは、理学療法学科 昼間部教員の塚本です。
最近、理学療法士に興味のある方とお話させていただくことが増え、どう説明したら理学療法士の仕事を伝えやすいかなぁと改めて考えるようになりました。

理学療法とは
“身体に障害のあるものに対し、その基本的動作能力の回復を図るため、様々な手段を加えること”
とされています(一般的に)。
…が!
個人的には
“患者さんが笑顔になれるお手伝いをすること”
だと思っています。
なぜなら、理学療法が対象となる患者さんの中には手足が麻痺して動かない方、足を切断してしまった方、余命数ヶ月と宣告された末期がんの方など、回復が難しい方もたくさんいらっしゃるからです。
そんな患者さんにどんな理学療法を提供すればいいのか?
患者さんの状態によって異なりますし、答えは1つではありません。
ただ、どんな場合にもいえることが
“患者さんの気持ちに寄り添って、どうやったらその患者さんが笑顔になれるのか考えること”
これが大切だと思います。
簡単なことではありませんが…つらそうだった患者さんの顔が笑顔になるたび、理学療法士となってよかったな~と感じます。

日リハでは
“即戦力となる理学療法士を養成する!”
という理念に基づき、
“患者さんの気持ちに寄り添う/共感できる医療人”
をテーマの一つに挙げ、人と繋がる学習に力を入れています。
具体的な内容や他の取り組みついては、学校のイベントでご紹介していますので、興味のある方はそちらにも足を運んでみてくださいね。