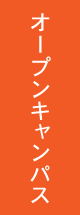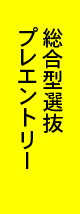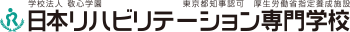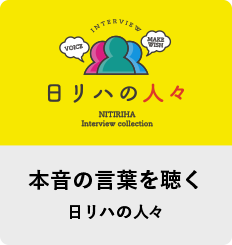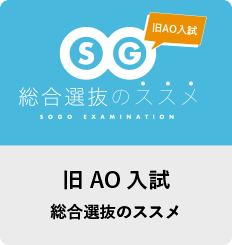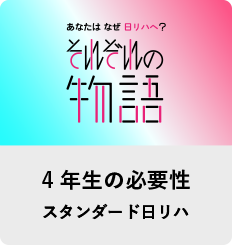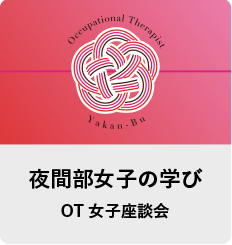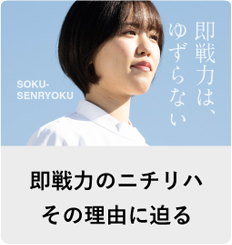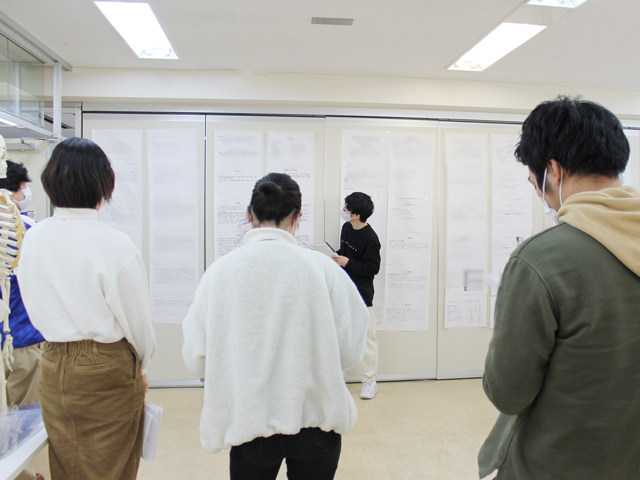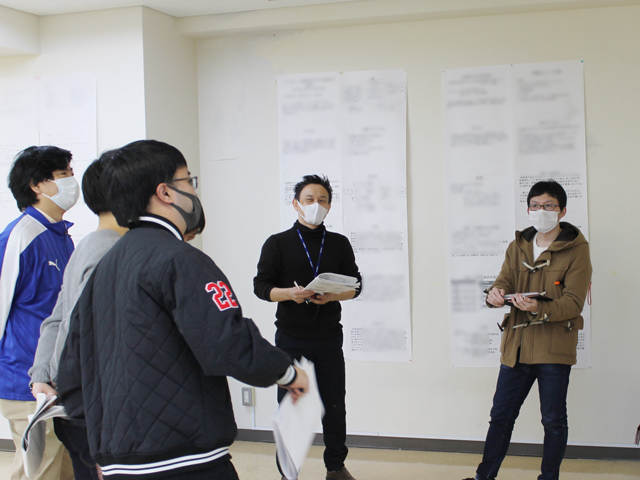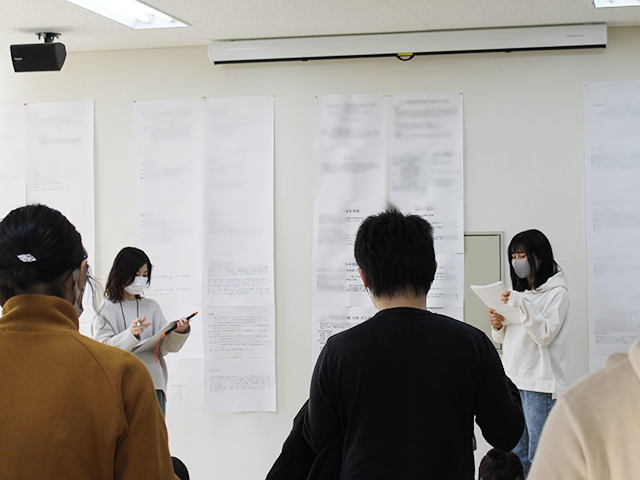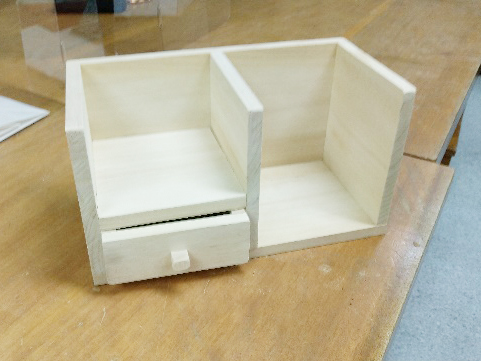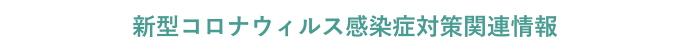皆さんこんにちは。作業療法学科、統括学科長の深瀬です。
この度、右の足首をねん挫し、松葉杖での生活を余儀なくされました。

一生の不覚です…
学生さんにもご心配をかけているところです。「先生!大丈夫ですか?」など温かいお言葉をいただいております。
ただ、普段から「作業療法士たるもの、自己管理が重要である」等と言ってきた身としては、お恥ずかしい限りです…
今回、怪我をしてみて、足が痛いときの患者さんの気持ちが良くわかりました。
◆ 右足が使えない事で、立ち上がれないし、歩けない。
◆ 立てない、歩けないことでトイレに行くのも億劫。
◆ 食事の準備もままならない。買い物にも行けないし…
◆ お風呂に入るのも大変、身だしなみなんか気にしている場合じゃない。
◆ 洗濯、掃除は後回し。
などなど、生活に不自由が出てきます。
作業療法士としては、障がいがあっても最大限使える機能や能力を生かして「その人なりの最大限の自立」を目標にして治療、指導を行いますが、今回はその難しさを知ることが出来たと思います。
足の痛みは、この冬休みで何とか完治させ、この経験をもとに、障がいを持つ方々が、何に困っているか?などを授業に生かしていこうと思っています。

転んでもタダでは起きない性格なので
この一年、皆さんにも新型コロナの影響で「友達と会食できない」「実家に帰省が出来ない」等、不自由が求められていると思います。
せっかくの年末年始ですが、我慢を強いられていると思います。この不自由な生活は、もう少し続きます。
でも、この経験は、私にも、皆さんにも「何かに気づき、成長をもたらす経験」になると思います。「冬来たりなば春遠からじ」です。
皆さんの努力によって、必ず実を結ぶ春が来るはずです。その日を待ちつつ、
くれぐれも、ご自愛ください。