-目次-
- 「生きがい作り」にも繋がる「藤細工」の授業
- リハビリ患者様をお招きした、「発達障害評価学」の授業
- 感覚検査の授業
「生きがい作り」にも繋がる「藤細工」の授業
「基礎作業学演習」という科目の中で”藤細工”を行っており、上肢・手指機能の改善や両手の協調性、注意機能、集中力等に対しての働きかけが可能なリハビリの授業です。

この授業では決して、”藤細工”を上手に芸術的に作ることが目的ではありません。
- 一般的な作業手順を覚え、将来の患者様、利用者様に指導ができるようになること
- 作業活動に必要とされる能力を見極められるようになること(適・不適な疾患、症状)
- 治療的効果・活動の意義を理解する
- 難易度や段階付けとともに作業への工夫を学ぶ
- 管理・安全への配慮を学ぶ
ができるように勉強していきます。
よく学校説明会で、こんな質問があります。
「私は不器用で、手工芸などの作業が苦手です。そんな私でも作業療法士になれるか不安です。」
大丈夫です!むしろ不器用な人ほど、思うように手足が動かせないリハビリ患者様の気持ちをより理解しながら指導ができる作業療法士を目指せるのではないでしょうか。
リハビリ患者様をお招きした、「発達障害評価学」の授業
次は、実際に障がいを持った方を作業療法学科の授業にお招きした、「発達障害評価学」という授業をご紹介します。
この授業は、現場に強い作業療法士を育てる一環として行っています。
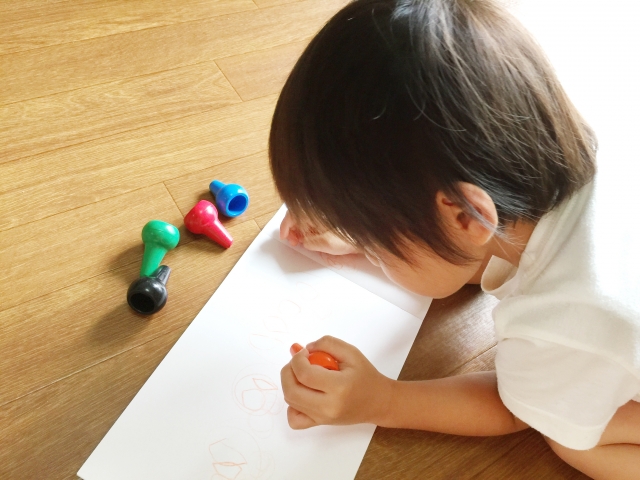
発達障害の子どもたちを理解するために必要とされる評価方法を身に付けることを目的としています。学生たちは少人数のグループに分かれてこの日のために準備を重ね、障がい者と関わるメニューを自分自身が考えました!
授業に協力してくれる方は日リハの先生が作業療法士として関わってきた方たちです。実際に障がいを持った方が授業に協力してくれることは日リハだからできる、即戦力養成のための取り組みの一環です。
感覚検査の授業
最後は「作業療法評価学」という実技中心の授業をご紹介します。
今回学生のみなさんに学んでもらったのは感覚の検査です。
感覚というのはいろいろ種類があり、触れたことが分かる触覚や、鋭利なものに触れた時に感じる痛覚、温かいもの冷たいものを感じる温度覚など他にもたくさんあります。

このような感覚機能が病気や怪我などにより鈍くなったり、失われたりすることがあります。身体のどこの部分に障害があり、リハビリテーションを行う必要があるのかを検査によって把握し治療を行っていきます。
授業では、感覚検査用の器具を使った検査を実際にやってみました。尖端の太さの違うフィラメントを検査する部分に当て行います。
また、お湯と冷たい水がそれぞれ入っている試験管を検査する部分にあて、お湯か水かを判別する、といった実際体験してみる授業を行っています。
今回紹介した授業はほんの一部ですが、本校ではこういった実践的な授業を日々行い、現場で活躍できる作業療法士を輩出しています。また、実践的な授業を行うことで「将来の自分」がイメージしやすくなるため、座学や試験勉強においてもより深い理解を得ることができます!
